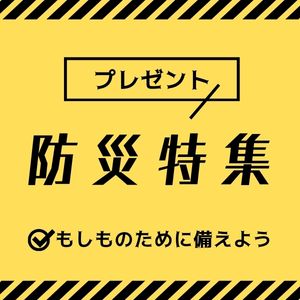立山博物館
鮮やかな「地獄」に 自分見つめ直す

江戸時代に立山登拝の拠点村落の一つだった富山県立山町芦峅寺(あしくらじ)集落にある当館は、展示館を中心に施設が点在する広域分散型博物館です。立山の人と自然にかかわる資料約2万点を収蔵し、常設展などで展示しています。
「立山曼荼羅(まんだら)」は、罪を犯すと山中の地獄に落ちるが、立山の神仏によって救われるという立山信仰の世界観を絵で伝えるためのもの。芦峅寺や岩峅寺の宿坊家などに伝わり、現在53点が残っています。
吉祥坊本(きっしょうぼうほん)は、三河国岡崎藩第5代藩主の本多忠民(ただもと)が芦峅寺の宿坊家だった吉祥坊に寄進したものです。制作者がわかる立山曼荼羅は数少ないですが、この作品は左下に林豊(りんほう)、右下に登光齋林龍(とうこうさいりんりゅう)という名と、慶応2(1866)年に制作されたことが書かれています。
立山曼荼羅の多くは、立山連峰のうち浄土山から剱岳までの景観が描かれ、左端の剱岳は地獄の針山として、登ってはいけない山に描かれています。吉祥坊本は色合いがきれい。絵も細かく、特に地獄の様子が大きく丁寧に描かれています。
曼荼羅に向かい合うことは立山を拝むことと同じと考えられ、江戸時代には自分を見つめ直すきっかけにも使われていたため、多くの地獄が描かれています。称名滝など立山の名所や伝説も多く描き込まれているので、実際の名所と見比べてみるのも面白いです。
「銅錫杖頭(どうしゃくじょうとう)(剱岳発見)」は、1907(明治40)年に陸軍参謀本部陸地測量部測量官の柴崎芳太郎の一行が、人跡未踏の山と信じられていた剱岳頂上を極めた時に鉄剣とともに発見し、持ち帰ってきたものです。
錫杖は山で修行する人たちの杖ですが、輪郭がうちわ状で輪の下部は蕨(わらび)手形の様式から、平安初期に作られ、実用品というより奉納品だった可能性が高いとされています。山頂に残っていたものにしては保存状態が大変よいのが特徴です。
(聞き手・本多昭彦)
《立山博物館》富山県立山町芦峅寺93の1(☎076・481・1216)。[前]9時半~[後] 5時(入館は30分前まで)。展示館は300円。原則[月]休み。

学芸員 細木ひとみ さん ほそき・ひとみ 神戸女子大学大学院文学研究科日本史学専攻博士後期課程単位取得満期退学(日本民俗学)。2017年から現職。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
世田谷美術館 40年前の開館当時から 「日々を豊かにする美術」を発信し続けた逸品
-
鶴岡市立藤沢周平記念館 「ごますり」「ど忘れ」「祝(ほ)い人(と)」ーー連作短編集「たそがれ清兵衛」は8編それぞれ、特異な物腰や風貌(ふうぼう)、極端な性格ゆえにあだ名をつけられた武士が主人公です。
-
日本オリンピックミュージアム 日本オリンピックミュージアム
-
カスヤの森現代美術館 森の中で開眼。戦後アートシーンを代表する現代アートに触れる
新着コラム
-
-
グッとグルメ 古川昌希さん
イタリア料理ブカティーニ ビーフピラフ 小学生の頃から通っている大好きなお店です。ピラフと言えばパラパラご飯のイメージですが、これはしっとり系。今まで食べたことのないピラフでしたね。 -