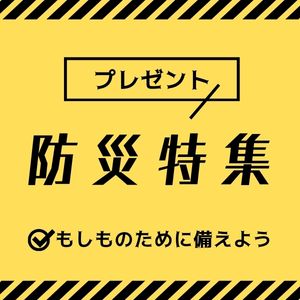国立アイヌ民族博物館
木彫の腕前 異性にもアピール

当館はアイヌ文化の復興・発展の拠点ウポポイ(民族共生象徴空間)の中核として昨夏開館しました。アイヌ民族の伝統技術や精神世界、アイヌ語を伝える資料など1万点以上を所蔵しています。
自然の中に生きてきたアイヌ民族は、自然や動植物、道具などにラマッ(霊魂)が宿ると考え、中でも重要なものをカムイと呼び祈りを捧げました。山や川に入る時はあいさつをし、狩りの無事を願います。木を切る時、動物を解体する時は感謝を表します。身の回りの生活用品は木や動物の角や骨で作り、彫刻などで飾ります。
「マキリ」(小刀)は動物を解体したり、木彫に用いたり、包丁として使ったり、誰もが常時携帯していた道具です。鞘にはイタヤカエデやイチイ、クルミなどの木材を用います。プロポーズの際、男性が女性に自作のマキリを贈ることもありました。硬い木に上手に文様を彫れるのは、手先が器用な証拠です。そんな男性なら狩猟もうまく、暮らしに困らないと女性にアピールできたのでしょう。
写真の作品は、木材と鹿の角を組み合わせ、桜の樹皮を通した装飾性の高いもの。根付けは熊の爪です。熊はアイヌ民族にとって位の高いカムイの一つ。捕獲した熊の子どもは、人間の世界へ遊びに来たお客様として大切に育てました。肉や毛皮などを得た後は、丁重な儀式でカムイの世界へ送り返し、再び人間の世界に来てくれるよう願ったのです。
直接料理を盛り付けることもあった「イタ」(お盆)にはカツラやシナなど軟らかい木材を使います。両面に彫刻したこのイタは、CT画像で見ると最も薄い部分で0・2ミリしかなく、木彫技術の高さがうかがえます。
アイヌ語を第一言語とする当館では、スタッフもアイヌ語名を持ち名札に記しています。来館の折には、名前の由来を聞いてみてください。
(聞き手・山田愛)
《国立アイヌ民族博物館》北海道白老町若草町2の3の1。7月16日までは午前9時~午後6時(土日祝は8時まで)。2点は5月23日まで展示。原則月、年末年始休み。ウポポイの日付指定入場券と入館日時予約が必要(詳細は公式ウェブサイトへ)。
|
学芸員 竹内イネトプ たけうち・いねとぷ 札幌市生まれで、母方がアイヌ民族の家系。イネトプは館内で使う通称(イネは4、トプは竹の意味)。前身の旧アイヌ民族博物館に2015年から勤務。資料のデータベース管理や調査などを担当。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
世田谷美術館 40年前の開館当時から 「日々を豊かにする美術」を発信し続けた逸品
-
鶴岡市立藤沢周平記念館 「ごますり」「ど忘れ」「祝(ほ)い人(と)」ーー連作短編集「たそがれ清兵衛」は8編それぞれ、特異な物腰や風貌(ふうぼう)、極端な性格ゆえにあだ名をつけられた武士が主人公です。
-
日本オリンピックミュージアム 日本オリンピックミュージアム
-
カスヤの森現代美術館 森の中で開眼。戦後アートシーンを代表する現代アートに触れる
新着コラム
-
-
グッとグルメ 古川昌希さん
イタリア料理ブカティーニ ビーフピラフ 小学生の頃から通っている大好きなお店です。ピラフと言えばパラパラご飯のイメージですが、これはしっとり系。今まで食べたことのないピラフでしたね。 -