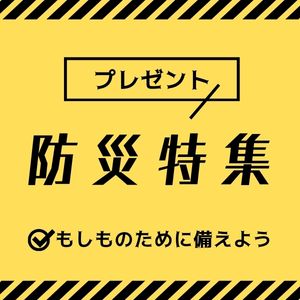マッチ たばこと塩の博物館
ラベルやケースに創意工夫

19世紀前半にヨーロッパで発明されたマッチの製造が、アジア諸国に先駆けて日本で本格化したのは明治前期です。国内産業の育成を目指していた政府も生産を奨励。熟練を要さない工程が多く、貧しい旧士族らの就労にも役立ちました。材料の木材を国内で調達できたこともあって、1890~1910年代には、日本は世界屈指のマッチ輸出大国になりました。
当館は、明治~昭和時代のマッチラベル約10万点、マッチケース約250点を所蔵しています。その一部を公開する特別展(7月7日まで)の展示品から、黄金時代の品を紹介します。
マッチは本体の見た目が他社製品と区別しにくいため、箱のラベルのデザインに創意工夫が施されました。デザインには発注者の意向が反映されています。主要な輸出先の中国では、福(子宝)、禄(財産)、寿(長寿)に通じるモチーフが好まれました。3体の像が並んだ図柄はまさに福禄寿。シカの図柄は、禄と音が同じ「鹿」を射ることで禄を得ることを表しています。獅子も吉祥のモチーフですね。
金属製のマッチケースは、マッチを安全に収納、携帯するためのもの。一時期作られていた「黄リンマッチ」は、何に摩擦させても着火でき、便利な半面、危険性も高かったのです。この「ブック形銅製マッチケース」は、側面にマッチを擦るためのヤスリがついています。ブーツ形や魚形なども作られ、ヤスリの位置にデザイン上の工夫が見られます。
(聞き手・牧野祥)
《たばこと塩の博物館》 東京都墨田区横川1の16の3(問い合わせは03・3622・8801)。午前10時~午後6時(入館は30分前まで)。100円。月曜(祝・休日の場合は翌日)休み。
|
学芸員 青木然 あおき・ぜん 2014年から現職。専門は日本近現代史。現在開催中の特別展「マッチ 魔法の着火具・モダンなラベル」を担当。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
世田谷美術館 40年前の開館当時から 「日々を豊かにする美術」を発信し続けた逸品
-
鶴岡市立藤沢周平記念館 「ごますり」「ど忘れ」「祝(ほ)い人(と)」ーー連作短編集「たそがれ清兵衛」は8編それぞれ、特異な物腰や風貌(ふうぼう)、極端な性格ゆえにあだ名をつけられた武士が主人公です。
-
日本オリンピックミュージアム 日本オリンピックミュージアム
-
カスヤの森現代美術館 森の中で開眼。戦後アートシーンを代表する現代アートに触れる
新着コラム
-
-
グッとグルメ 古川昌希さん
イタリア料理ブカティーニ ビーフピラフ 小学生の頃から通っている大好きなお店です。ピラフと言えばパラパラご飯のイメージですが、これはしっとり系。今まで食べたことのないピラフでしたね。 -