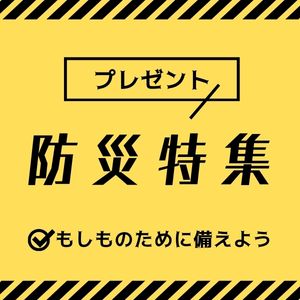復元建造物 江戸東京たてもの園
昭和の世相を映したデザイン

当園は1993年、東京都江戸東京博物館の分館としてオープンしました。歴史的価値があり、取り壊されてしまう建築物30棟を移築・復元しています。
「武居三省堂」は昭和初期、東京・神田の書道具店でした。間口が狭く奥行きがあり、正面はフラットで防火対策のためタイル張り。関東大震災の教訓から、燃えにくい素材で正面を覆った「看板建築」の典型です。三階建てに見えますが、当時は三階以上に居室をつくってはいけませんでした。そこで勾配が緩やかな屋根をのせ、できた空間を居室ではなく屋根裏部屋と言っていたんですね。
武居三省堂は神田界隈に多かった細長い地所をうまく使った建物でもあります。店内片側の壁一面の棚には約350の引き出しがあり、様々な筆が収められていました。天井にはストックを置く吊り棚、陳列台に隠された階段を下ると荷ほどきをする地下室。限られた空間を有効に使う工夫が感じられます。
対照的に「子宝湯」は堂々とした外観で、「東京型銭湯」と呼ばれています。唐破風の下の彫刻だけで家が建つほどの経費がかけられたとか。建物内部の格子状の天井は格式高い「折上げ格天井」。贅を尽くした建築が、庶民の使う銭湯というそのギャップが面白いですね。
復元建造物は、かつて使われていた時代を再現しています。武居三省堂も子宝湯も昭和30年代の設定。墨汁などの当時の商品や柱時計などを配し、生活を感じられるようにしています。
(聞き手・小森風美)
《江戸東京たてもの園》 東京都小金井市桜町3の7の1、都立小金井公園内(問い合わせは042・388・3300)。午前9時半~午後5時半(10月~3月は4時半まで。入園は30分前まで)。400円。(月)((祝)(休)の場合は翌日)休み。
|
学芸員・阿部由紀洋 あべ・ゆきひろ 1992年、江戸東京たてもの園を管理する江戸東京歴史財団(現・都歴史文化財団)入職。主に商店建築が並ぶ東ゾーン担当。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
世田谷美術館 40年前の開館当時から 「日々を豊かにする美術」を発信し続けた逸品
-
鶴岡市立藤沢周平記念館 「ごますり」「ど忘れ」「祝(ほ)い人(と)」ーー連作短編集「たそがれ清兵衛」は8編それぞれ、特異な物腰や風貌(ふうぼう)、極端な性格ゆえにあだ名をつけられた武士が主人公です。
-
日本オリンピックミュージアム 日本オリンピックミュージアム
-
カスヤの森現代美術館 森の中で開眼。戦後アートシーンを代表する現代アートに触れる
新着コラム
-
-
グッとグルメ 古川昌希さん
イタリア料理ブカティーニ ビーフピラフ 小学生の頃から通っている大好きなお店です。ピラフと言えばパラパラご飯のイメージですが、これはしっとり系。今まで食べたことのないピラフでしたね。 -