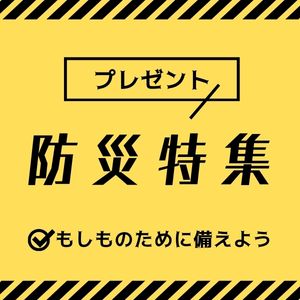妖怪の意匠 三次もののけミュージアム
恐怖の対象 一方で身近な存在に

江戸時代の妖怪物語「稲生物怪録(いのうもののけろく)」の舞台となった広島県三次(みよし)市に立つ当館は、私が30年以上かけて集めた妖怪にまつわる資料約5千点を収蔵しています。「もののけ」で町おこしを目指す同市が、私の寄贈品をもとに設立、昨年4月に開館しました。
自然に対する畏怖(いふ)や心の不安から生み出された妖怪。室町時代の「百鬼夜行(ひゃっきやぎょう)絵巻」が知られていますが、それ以前から言い伝えや書物に登場します。木版技術が発達した江戸時代、妖怪を描いた錦絵や版本が庶民にも浸透し、妖怪は恐怖の対象の一方で身近な存在にもなりました。それに伴い、日用品にも妖怪の意匠が施されるようになります。
コレクションは絵巻や錦絵をはじめ、着物や根付け、刀の鍔(つば)、器、玩具など、江戸~昭和時代の品々。「妖怪文化」の広がりを見ることができます。
「鵺図刺子半纏(ぬえずさしこばんてん)」は、大正~昭和時代の消防組のもの。裏側に染められているのは、顔は猿、足は虎、尾は蛇という異形の姿の怪獣「鵺」。平安時代後期の武将源頼政が退治したと伝えられています。
江戸時代から粋を身上とした火消しの半纏には妖怪が大胆にデザインされてきました。人々を驚かせようという意図でしょう。鎮火して帰るときに裏返して派手な絵柄を見せたと言われています。
妖怪は根付けにも多用されました。「河童図饅頭根付(かっぱずまんじゅうねつけ)」は、人間の「尻子玉」(肛門内にあると想像された玉)を抜こうとする河童をおならで退治する様子が獣骨に彫られています。
(聞き手・牧野祥)
《湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)》 広島県三次市三次町1691の4(問い合わせは0824・69・0111)。午前9時半~午後5時。半纏は3月10日までの企画展、根付けは常設展で展示。600円。原則(水)休み。
|
名誉館長 湯本豪一 ゆもと・こういち 妖怪研究家。川崎市市民ミュージアム学芸員、学芸室長を経て、現在は法政大学大学院で教える。著書に「江戸の妖怪絵巻」など。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
世田谷美術館 40年前の開館当時から 「日々を豊かにする美術」を発信し続けた逸品
-
鶴岡市立藤沢周平記念館 「ごますり」「ど忘れ」「祝(ほ)い人(と)」ーー連作短編集「たそがれ清兵衛」は8編それぞれ、特異な物腰や風貌(ふうぼう)、極端な性格ゆえにあだ名をつけられた武士が主人公です。
-
日本オリンピックミュージアム 日本オリンピックミュージアム
-
カスヤの森現代美術館 森の中で開眼。戦後アートシーンを代表する現代アートに触れる
新着コラム
-
-
グッとグルメ 古川昌希さん
イタリア料理ブカティーニ ビーフピラフ 小学生の頃から通っている大好きなお店です。ピラフと言えばパラパラご飯のイメージですが、これはしっとり系。今まで食べたことのないピラフでしたね。 -