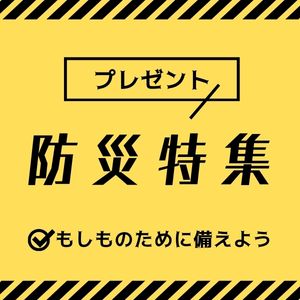酒の文化資料 「食と農」の博物館
宴席を楽しむ 粋な仕掛け

東京農大に付属する当館のコレクションは、大学の研究分野に関わる資料です。鶏の剥製(はくせい)やクリオネの実物、農具など多岐にわたりますが、収集の柱の一つは、醸造科学科創設者の住江金之(すみのえきんし、1889~1972)が集めた酒の文化資料。日本各地の酒器など約200点を所蔵しています。
日本の酒造りの起源は古く、神事と深く結びついてきましたが、時代が下ると庶民も広く楽しむものになりました。特徴は、「温めても冷やしても良し」。器にも熱伝導性や耐熱性の高い材質を使うほか、屋外で熱燗(あつかん)を作る専用器もあります。
一方で、酒席を楽しむための工夫も様々です。「鶯徳利(うぐいすとっくり)」は酒を注ぐ時、「キュキュッ」と音が鳴ります。内部を二つに仕切った構造で、器を傾けることで内部の気圧が変化し、上部の穴から音が出る仕組み。「鶯杯」も、縁にある穴に口をつけて酒を飲む時に音が出ます。酒器で宴を盛り上げる、粋な心の表れでしょう。
酒との関わりを示す錦絵も所蔵し、資料保護のためレプリカを展示しています。そこに描かれた酒癖や大酒大会の様子には、今も昔も変わらない、宴を楽しむ姿があります。「江戸時代の居酒屋の風景」は明治維新期の風刺絵。酒を飲む二人の着物柄に注目すると、左の人物は籠目(かごめ)模様と縞(しま)模様の上下で「鹿児島」、右の人物は萩と蝶の模様で「長州」を連想させます。犬猿の仲だった薩長の接近を、酒を酌み交わす描写で表現しています。
(聞き手・木谷 恵吏)
《東京農業大学「食と農」の博物館》 東京都世田谷区上用賀2の4の28(問い合わせは03・5477・4033)。午前10時~午後5時。原則月、毎月最終火休み。無料。2点は常設展示。
|
学芸員 西嶋優 にしじま・まさる 東京農大農学部卒。2011年から同館勤務。4月25日~8月5日の企画展「農芸化学の始まりから未来まで」を担当。
|
私のイチオシコレクションの新着記事
-
世田谷美術館 40年前の開館当時から 「日々を豊かにする美術」を発信し続けた逸品
-
鶴岡市立藤沢周平記念館 「ごますり」「ど忘れ」「祝(ほ)い人(と)」ーー連作短編集「たそがれ清兵衛」は8編それぞれ、特異な物腰や風貌(ふうぼう)、極端な性格ゆえにあだ名をつけられた武士が主人公です。
-
日本オリンピックミュージアム 日本オリンピックミュージアム
-
カスヤの森現代美術館 森の中で開眼。戦後アートシーンを代表する現代アートに触れる
新着コラム
-
-
グッとグルメ 古川昌希さん
イタリア料理ブカティーニ ビーフピラフ 小学生の頃から通っている大好きなお店です。ピラフと言えばパラパラご飯のイメージですが、これはしっとり系。今まで食べたことのないピラフでしたね。 -