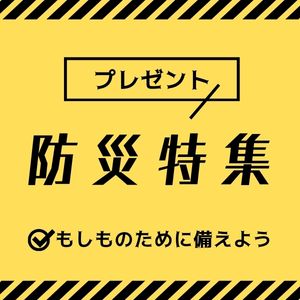明治大学平和教育登戸研究所資料館
軍事遺物が語る 加害の実相

資料館の建物は、アジア・太平洋戦争中に旧日本陸軍が生物兵器などの開発に使っていたものです。戦後は明治大学農学部の実験室になっていましたが、市民運動などからの要望を経て、2010年に資料館として開館しました。
展示品の一つが「石井式濾水機濾過筒」の現物です。近くで見ると、「軍事秘密」と刻印されています。珪藻土とアルミニウムで構成された濾過筒に水を染みこませ、筒の中心から浄水が出る仕組みです。戦地では、汚水で細菌に感染して命を落とす人もいました。そこで1938年、陸軍731部隊(石井部隊)が戦地での飲み水用に開発したとされています。
本来水質が悪い場所で使うはずが、細菌戦が行われたとされる中国戦線で、この濾水機を持ち込んで水を確保したという記録があります。細菌戦に備えて日本軍の飲み水を確保する裏の顔があったと考えると、兵士を守る道具と、他国を攻める道具を同時に開発していたことになります。
太平洋戦争末期を象徴する兵器が「風船爆弾」です。44年に完成した兵器で、こんにゃくのりで和紙をつなぎ合わせた気球に、焼夷弾などを取り付けました。展示品は10分の1のレプリカですが、実際は直径約10メートルあったそうです。
全国約100校から動員された女子学生が目的も知らされずに徹夜で風船を作り続けました。劣勢の日本が米国を直接攻撃する唯一の手段と考えられたのです。携わった体験者からは「大変な作業だったが完成させなければと必死で、弱音を吐くことさえ思いつかなかった」という声が多く寄せられています。
一見、荒唐無稽に思われますが、偏西風にのって約9300発中約千発が米国本土に到達。オレゴン州では不時着した爆弾に触れた6人が亡くなりました。
戦争被害の記憶の継承も大切ですが、被害と加害は表裏一体。戦後80年を迎え、体験していない人間が学び、引き継ぐことが大事です。
(聞き手・大石裕美)
《明治大学平和教育登戸研究所資料館》 川崎市多摩区東三田1の1の1(☎044・934・7993)。午前10時~午後4時。無料。原則日曜日、月曜日、火曜日休み。企画展「風船爆弾作戦と本土決戦準備 ―女の子たちの戦争―」は8月30日まで。

館長 山田朗さん 明治大学文学部教授。東京都立大大学院人文科学研究科修了。1999年から現職。専攻は日本近現代史、軍事史。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
世田谷美術館 40年前の開館当時から 「日々を豊かにする美術」を発信し続けた逸品
-
鶴岡市立藤沢周平記念館 「ごますり」「ど忘れ」「祝(ほ)い人(と)」ーー連作短編集「たそがれ清兵衛」は8編それぞれ、特異な物腰や風貌(ふうぼう)、極端な性格ゆえにあだ名をつけられた武士が主人公です。
-
日本オリンピックミュージアム 日本オリンピックミュージアム
-
カスヤの森現代美術館 森の中で開眼。戦後アートシーンを代表する現代アートに触れる
新着コラム
-
-
グッとグルメ 古川昌希さん
イタリア料理ブカティーニ ビーフピラフ 小学生の頃から通っている大好きなお店です。ピラフと言えばパラパラご飯のイメージですが、これはしっとり系。今まで食べたことのないピラフでしたね。 -