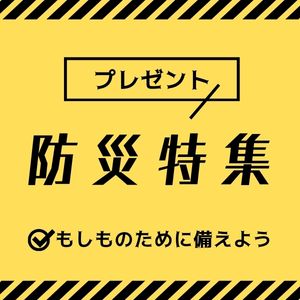芝居絵びょう風 絵金蔵
ろうそくの明かりに浮かぶ赤

幕末から明治初期にかけて、高知で活躍した絵師・弘瀬金蔵(1812~76)。通称「絵金」は狩野派に学び、土佐藩の御用絵師を務めた後、今の香南市赤岡町に暮らしました。回船業で栄えた商人たちの依頼で、地元の須留田八幡宮などで演じられた芝居の場面を二曲一隻の屏風に多数描き残しました。
当館は、個人宅の蔵に残されていた23点の芝居絵屏風を収蔵・展示するため2005年に開館しました。毎年7月、ろうそくとちょうちんの明かりの下、商店街の軒先に作品を並べる「須留田八幡宮神祭」の様子を再現した常設展示はレプリカですが、作品収蔵庫に開けた「蔵の穴」から、月替わりで2点ずつ、本物を鑑賞できます。
構図の美しさが強い印象を与える「伊達競阿国戯場 累」は絵金の代表作の一つです。「血赤」と呼ばれる迫力のある赤色が特徴的で、右側の女性の着物、中央の主人公・累のじゅばん、左手前の男性の帯などに効果的に配されています。姉の怨念で醜い顔に変えられた累の左目にはろうが塗られ、ろうそくの明かりに照らされると光って見えることもあります。
白描と呼ばれる、芝居絵屏風の下絵も数百点残されています。「『菅原伝授手習鑑』寺子屋の場 松王と春藤玄蕃」の、滑らかで力強く迷いのない線からは、動きを再現する表現力、画力の高さをうかがい知ることができます。絵金が、他の町絵師とは段違いの実力を持っていたことを感じさせます。
(聞き手・高田倫子)
《絵金蔵》 高知県香南市赤岡町538
(問い合わせは0887・57・7117)。
午前9時~午後5時(入館は30分前まで)。
520円。
月曜休み。
芝居絵屏風は、巡回展「奇才 江戸絵画の冒険者たち」
(7月7日から山口県立美術館など)で展示予定。

学芸員 吉川琴子 よしかわ・ことこ 高知市出身。高知大を卒業後、2017年から同館勤務。芝居絵屏風の保存修理などに関わる。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
世田谷美術館 40年前の開館当時から 「日々を豊かにする美術」を発信し続けた逸品
-
鶴岡市立藤沢周平記念館 「ごますり」「ど忘れ」「祝(ほ)い人(と)」ーー連作短編集「たそがれ清兵衛」は8編それぞれ、特異な物腰や風貌(ふうぼう)、極端な性格ゆえにあだ名をつけられた武士が主人公です。
-
日本オリンピックミュージアム 日本オリンピックミュージアム
-
カスヤの森現代美術館 森の中で開眼。戦後アートシーンを代表する現代アートに触れる
新着コラム
-
-
グッとグルメ 古川昌希さん
イタリア料理ブカティーニ ビーフピラフ 小学生の頃から通っている大好きなお店です。ピラフと言えばパラパラご飯のイメージですが、これはしっとり系。今まで食べたことのないピラフでしたね。 -