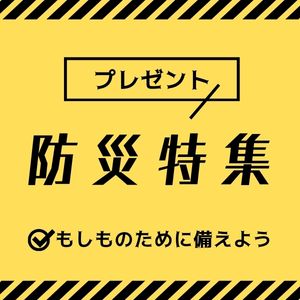鍋島緞通 鍋島緞通吉島家 緞通ミュージアム
綿で織り上げた殿様の「座布団」

江戸中期、佐賀の町人が長崎・出島で中国人から織りの技術を学び持ち帰ったのが鍋島緞通の始まりです。佐賀藩鍋島家は献上品として生産を奨励する一方、技術を門外不出としました。禁制が解かれた明治以降は一般に流通。1912年創業の当社は、技術を継承し現在の鍋島緞通の基礎を作りました。
鍋島緞通の織り方は基本的にペルシャじゅうたんなどと同じですが、素材は木綿です。日本では羊毛など動物性の素材が敬遠されたのと、有明海干拓で地中の塩分を抜くために綿花が栽培され、豊富だったためです。
土足で暮らす外国のじゅうたんはごみが入らないよう糸目を詰め毛足が短いのに比べ、室内で殿様が座布団のように使う鍋島緞通は毛足が長く、触り心地を重視。大きさは約1畳分です。上座と下座を区別するため、下座側だけに房がついているのも特徴です。
鍋島家藩主が使った「唐草花文淡灰地縁二重雷文(からくさかもんうすはいぢふちにじゅうらいもん)」は、朝香宮王女で13代当主に嫁いだ鍋島紀久子様より賜ったもの。藩主のみが使えた朱色を多用し、イチョウの葉をかたどった家紋、杏葉文をあしらっています。
古典柄が人気の「蟹牡丹灰白地縁二重雷文(がにぼたんはいしろぢふちにじゅうらいもん)」は、創業当時の当社製。中国で富や美の象徴とされる牡丹と、佐賀の方言でガニというカニを表します。紺の丸い部分が目で、四隅へ広がる緑の部分がはさみ。佐賀城のお堀にたくさんいた沢ガニとも、はさみを振る様が福を招くという有明海のシオマネキとも言われます。
(聞き手・山田愛)
《鍋島緞通吉島家 緞通ミュージアム》 佐賀市赤松町1の28(問い合わせは0952・24・0778)。
午前10時~午後5時。
年末年始休み。

はら・よしひさ 佐賀県唐津市出身。佐賀の農産品販売に携わったのち入社。営業部長として全国を回るかたわら、織師として自らも緞通を織る。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
世田谷美術館 40年前の開館当時から 「日々を豊かにする美術」を発信し続けた逸品
-
鶴岡市立藤沢周平記念館 「ごますり」「ど忘れ」「祝(ほ)い人(と)」ーー連作短編集「たそがれ清兵衛」は8編それぞれ、特異な物腰や風貌(ふうぼう)、極端な性格ゆえにあだ名をつけられた武士が主人公です。
-
日本オリンピックミュージアム 日本オリンピックミュージアム
-
カスヤの森現代美術館 森の中で開眼。戦後アートシーンを代表する現代アートに触れる
新着コラム
-
-
グッとグルメ 古川昌希さん
イタリア料理ブカティーニ ビーフピラフ 小学生の頃から通っている大好きなお店です。ピラフと言えばパラパラご飯のイメージですが、これはしっとり系。今まで食べたことのないピラフでしたね。 -