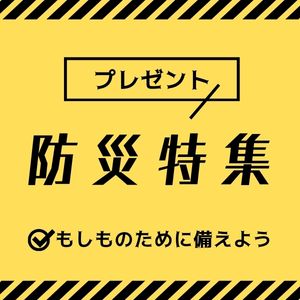地歌舞伎衣装 美濃歌舞伎博物館相生座
芝居根付く土地柄 熱気伝える

江戸時代、農民が演じる地歌舞伎は全国的に禁じられていました。中山道が貫き交通の要衝である美濃はその例外で、街道整備などの苦役の代償として黙認され、繁栄しました。
2棟の芝居小屋の一部を移築、合体した当館は地歌舞伎を秋に定期上演。江戸期から伝わる衣装や小道具など約5千点の一部を展示しています。
仙台藩伊達家のお家騒動を題材にした「伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)」の登場人物・政岡の衣装は、藩の家紋のモチーフである竹とスズメを用いるのが約束ごと。実子を犠牲にしながら主君を守る政岡の耐え忍ぶ心情を、雪をかぶったササの葉で表しています。
昭和初期に作られた本作では竹の幹が太く、南天の実がつけ加えられています。前の時代にはない特徴で、時代によって異なるデザインの衣装を公演ごとに使い分けています。
「黒天鵞絨地金繍龍門(くろびろうどじきんしゅうりゅうもん)に龍乗り貴人文」は花魁(おいらん)が着る打掛(うちかけ)。大きな柄、凝った刺繍(ししゅう)に加え、龍門の窓の部分に鏡をつけるなど当時最先端の素材や技法が目を引きます。派手好みの上方のもので、こうした衣装が残るのは、東西の中間に位置する美濃らしさと言えます。
2点を含め多くの衣装は、別布に刺繍した柄をアップリケのように縫い付けています。太い糸をとじ糸で留める駒刺繍を多用したり、柄の下に綿を入れたりしているのは、舞台で映える立体感を出すための工夫です。
当館は古い衣装を手本に新調する活動もしています。同じ材料がなく、現代人の体格に合う衣装づくりは試練ですが、先人の歌舞伎熱と知恵を、忠実に伝えたいと思っています。
(聞き手・鈴木麻純)
《美濃歌舞伎博物館 相生座》 岐阜県瑞浪市日吉町8004の25(問い合わせは0572・68・0205)。午前10時~午後4時。要予約。300円。原則(月)休み。

館長 小栗幸江 おぐり・さちえ 創立者の父・克介さん(故人)の後を継ぎ、1999年から現職。役者や裏方も務め、美濃歌舞伎子ども伝承教室では後進の育成にあたる。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
世田谷美術館 40年前の開館当時から 「日々を豊かにする美術」を発信し続けた逸品
-
鶴岡市立藤沢周平記念館 「ごますり」「ど忘れ」「祝(ほ)い人(と)」ーー連作短編集「たそがれ清兵衛」は8編それぞれ、特異な物腰や風貌(ふうぼう)、極端な性格ゆえにあだ名をつけられた武士が主人公です。
-
日本オリンピックミュージアム 日本オリンピックミュージアム
-
カスヤの森現代美術館 森の中で開眼。戦後アートシーンを代表する現代アートに触れる
新着コラム
-
-
グッとグルメ 古川昌希さん
イタリア料理ブカティーニ ビーフピラフ 小学生の頃から通っている大好きなお店です。ピラフと言えばパラパラご飯のイメージですが、これはしっとり系。今まで食べたことのないピラフでしたね。 -