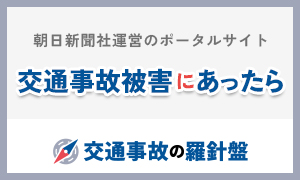米どころの餅文化、甘く辛く慕わしく 岩手・一関

餅にはちょっとうるさいとの自負がある。わが叔母が大の餅搗き好きで、年末には親類縁者を集めて盛大に餅つきを開催し、わたしも長らくその手伝いに加わっていたためだ。
叔母宅の餅搗きは一日で二十数臼、六十キロ以上の米を餅にするという、この家は餅屋なのか?と思うほどの量で、参加者全員が日が傾くまで働いても搗き終わらないこともあった。ただその癖、彼女自身はそんなに餅が好物というわけではなく、親しい人たちが集まってわいわいやっているのを見るのが好きだったらしい。そんなわけで彼女が亡くなった年の暮れには、従兄たちが「追悼の餅搗き」を開催し、にぎやかに彼女を偲んだ。
餅搗きの最大の楽しみは、出来立ての餅をその場で食べられること。もっとも叔母宅の餅搗きはとにかく人手が必要なため「働かざるもの食うべからず」状態だったが、先日、仕事でうかがった岩手県一関市で興味深いお話を聞いた。
全国的には餅といえば正月に食べられるもの。しかしこの地域では、江戸時代には月に二度、餅を搗く慣習があり、今日でも年中行事や人生のさまざまな節目に餅が作られるという。多種多様な味付けを施された餅が一汁三菜の形式で並ぶ餅本膳という料理も存在し、祝いごとはもちろん、葬式などの不祝儀の場でも餅が食べられるそうだ。
正しい餅本膳には、「おとりもち」と呼ばれる進行役の指示に従うとか、最初は大根おろしを食べ、最後にはたくわんで椀を清めるなど、細かな決まり事があるという。これは餅本膳が、この一帯を支配していた仙台藩の武家文化の中で生まれた料理であるため。現代ではこの伝統料理を気軽に体験できる店もあるとうかがい、早速お邪魔をした。
ずらりと並んだ餅は、小豆にくるみ、納豆、ゴマ等々、甘辛さまざまな味付けが施され、更にそこに汁物を兼ねた雑煮や本膳にも欠かせない大根おろしが添えられる。こう書くとすぐにおなかいっぱいになってしまうのでは?と思われる方もおいでだろうが、なにせすべてが搗き立ての餅なので、その柔らかさと温かさに惹かれて、ついついつるつるといただけてしまう。甘い餅と辛い餅の間に大根おろしをはさむことで口の中がさっぱりして、次の餅が美味しく食べられる。
中でも印象的だったのがじゅうね(じゅうねん)餅で、じゅうねん、つまりエゴマで餅を味付けしたもの。ぷちぷちという食感も楽しく、ゴマとは異なる香ばしさが癖になる味わいだった。
水を汲むこと、火を焚くこと、すべてが現代よりも手間がかかった時代には、餅は今日の我々とは比べ物にならぬほど手の込んだ食べ物に位置づけられていたはずだ。それをこれほど多種多様な味付けで食べようとするのは、餅がいかにこの地に根付き、人々に親しまれてきた存在であるかを強く物語っている。同時に、この地が古くより、いかに豊かな米どころであるかという事実も。
そう思えば食物とは、ただエネルギーを摂取するだけの存在ではない。どういった食材をどのように食べるか。密接にからみ合ったその場所の歴史と文化が、もっとも親しみやすい形で提示されるのが、その土地に根付いた食べ物なのではあるまいか。
なお一関では二〇一二年から開催の全国もちフェスティバル(旧・全国ご当地もちサミットin一関)を始め、独自の餅文化の普及・振興に力を入れていらっしゃる。近年では全国的に、餅をカレーやチーズなど洋風の味付けで食べることも増えているが、これからもこの地はそういった新しい味覚も取り入れながら、餅が常に身近にある暮しを守ってゆかれるのだろう。
となると数年後に再び一関で餅をいただけば、これまでになかった味わいに出会えるのかもしれない。それが今から楽しみである。
|
澤田 瞳子 さわだ・とうこ 1977年生まれ。同志社大文学部文化史学専攻卒業、同大学院博士前期課程修了。2016年『若冲』で親鸞賞、21年『星落ちて、なお』で直木賞受賞。『赫夜』『孤城 春たり』など著書多数。 |
 Ⓒ富本真之 |
食彩を描く 澤田瞳子の滋味探訪の新着記事
-
何杯でも食べ歩く 沖縄のヒンヤリ「ぜんざい」 直木賞受賞作『星落ちて、なお』などで知られる澤田瞳子さん。実はご当地グルメを見ると目の色が変わってしまう、という秘められた生態の人です。そんな作家を唸らせる滋味の数々――なかでも「ここまでハマっている甘味はない」と断言する沖縄のぜんざいをご紹介します。
-
正月の静けさ、作家稼業にもってこい 冴える味わい土佐文旦 直木賞受賞作『星落ちて、なお』などで知られる澤田瞳子さん。実はご当地グルメを見ると目の色が変わってしまう、という秘められた生態の人です。そんな作家を唸らせる滋味の数々――今回は土佐文旦。
-
奈良にうまいものあり! ピリ辛スープにシャッキリ白菜 天理ラーメン 直木賞受賞作『星落ちて、なお』などで知られる澤田瞳子さん。実はご当地グルメを見ると目の色が変わってしまう、という秘められた生態の人です。そんな作家を唸らせる滋味の数々――今回は奈良県の天理ラーメン。
-
贅沢アジフライ+元寇 食と歴史の二重奏♪ 長崎・松浦 直木賞受賞作『星落ちて、なお』などで知られる澤田瞳子さん。実はご当地グルメを見ると目の色が変わってしまう、という秘められた生態の人です。そんな作家を唸らせる滋味の数々――今回は長崎・松浦の贅沢アジフライ。