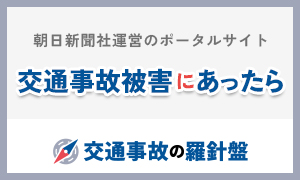洋食Bistro時遊 ポークジンジャーのランチ 7年前にできた店です。知り合いだった店長に頼まれて娘がアルバイトをしていました。私が初めて店を訪ねた際も働いていました。以来、月1回くらい足を運びます。

【SP】女ひとり 漱石の心見つめ
源川瑠々子さん
夏目漱石の『こころ』という作品を知っていますか。私がはじめて出会ったのは高校の教科書で、当時衝撃的な結末に心が震えたのを覚えています。そんな『こころ』をミュージカルとして舞台化する? しかも登場人物はひとり? 一体どんな舞台なのか、ということで、12月12日に東京・日本橋公会堂で開幕するひとり文芸ミュージカル『静-しず-』に出演される、舞台生活20周年を迎えた源川瑠々子さんにインタビューさせていただきました。(聞き手・中山幸穂)
※源川瑠々子さんは来年2月1日の朝日新聞夕刊「グッとグルメ」に登場します。写真で着用している着物は、同欄で源川さんがご紹介する「弁松総本店」のおかみさんから譲り受けたものです。
――12月12日に開幕する、ひとり文芸ミュージカル『静-しず-』は夏目漱石の作品『こころ』に登場する先生の奥さんの静の舞台ですよね。おもしろい視点だなあと感じました。
源川 そうですよね。中山さんは静さんについて、どんなイメージがありますか?
――名前通り落ち着いていて、あまり感情の起伏がみえない方という印象です。
源川 うん、『こころ』を読むとそう感じますよね。でも原文から静の言葉を抜き出してみたときに膨大な数のせりふが出てきたんです。読んでみたらかなり重要なことを言っていたりして、これは1本の芝居ができるという確信を得ました。
ひとり文芸ミュージカル とは?
歴史的文芸作品を原作とし、『バーバパパ世界をまわる』でJASRAC国際賞を受賞した神尾憲一が音楽・演出を務めるミュージカル。ひとり舞台という点が大きな特徴で、作品内の登場人物ひとりから見た視点で物語が語られていく。
もともとこのミュージカルを表現する言葉は存在しなかったが、ミュージカル評論家瀬川昌久の提案により「ひとり文芸ミュージカル」というジャンルが誕生した。
12月12日開幕のひとり文芸ミュージカル『静-しず-』とは?
夏目漱石作『こころ』に登場する「先生」の妻「静」から見た「こころ」の世界を表現する舞台。音楽は神尾憲一による生ピアノ演奏。2003年に『静-しず-』の前身となる『もうひとつの、こころ』が上演されて以来、年々進化しつつ再演されてきた。今回で10回目を迎える。
――実際に演じる中で静さんの言葉で特に印象的なせりふはありますか。
源川 「そりゃ女だから私には解りませんけれど」という言葉。この作品のキーワードになる言葉でもあり、静という一人の女性を抜き出した意図にもなるのかなという風に思いますね。
――そこに意味が詰まっているんじゃないかとお考えになられていると
源川 本当の意味での「女だからわからない」という意味もあるでしょうし、「だからあなたはどういう風に思う」という投げかけにも使われる言葉にもなる。静さんの深い言葉の使い方が読み取れるんです。明治女性の芯の強さと素直な気持ち、2つが見え隠れしているんじゃないかなと思います。
――静という役は20年ずっと演じ続けていらっしゃいますよね。演じ続ける中で自分の中での演じ方や解釈が変わってきたりしましたか。
源川 大きなところではそんなにないです。ただ見えてくるものっていうのがちょっと変わってはきますよね。やっぱり歳を重ねますので。言葉には表せない演じる時の心の置きどころというか。
あと舞台様式が当初とは大きく変わり、能舞台形式へと変化しました。今回日本橋公会堂さんで20年ぶりに帰って来てやらせて頂くんですけれども、そこでも能舞台の形式を作るので、初期にやらせていただいた感じとは全然異なります。能舞台では目に見える大きな場面転換がないので、お客様それぞれに想像力豊かに感じていただけたらいいなと思います。
――舞台が楽しみです。そもそも源川さんが俳優の道に進んだきっかけは何だったのでしょうか。
源川 とにかく体を動かすことが好きな子どもで、自分が歌ったり踊ったりしている姿を見て家族が笑顔になる光景が好きだったんです。そこから歌も踊りもお芝居も全部できるミュージカルの舞台に立ちたいと考えるようになりました。
――でも実は歌に自信がなかったそうですね。
源川 そう。最初全く歌に自信がありませんでしたが、作曲家の神尾憲一先生と出会ったことで歌への思いが変わりました。毎回私の声の特性を活かしたオリジナルの曲を作ってくださるからこそ20年続けてこられました。
――源川さんのための曲なんですね。
源川 今まで演じているミュージカル自体も、私を見てこういう舞台、役にしよう、と考えてくださったものです。
――では、「文芸ミュージカル」も源川さんのお人柄が反映されてできたもの?
源川 そうですね。ある日着物を持っていないか聞かれて、祖母に「おばあちゃまこういうお着物あるかしら」と電話したんですね。それを神尾先生が聞いていらして、「おばあちゃま」って言うお家なんだー…と。
――私も少しだけびっくりしました。
源川 私はそう呼ぶのが当たり前だったんですけどね。この事と、着物がある家だということに先生がピンと来て、お着物を着る役になりました。そして『こころ』という作品を先生が構想中だったこともあり、2つが重なって今のミュージカルの原型ができました。
実は、『静-しず-』の前身となる『もうひとつの、こころ』のお稽古中は先生役と書生役の方もいたんです。段々静ひとりの目線から見た方が、より夏目漱石の心が深く見えてくるんじゃないかという流れになって。自然とひとり文芸ミュージカルの形になっていっていきました。
――大きな舞台に立ちたいという思いはなかった?
源川 いや元々は立ちたいと思ってましたよ。帝劇で憧れた俳優さんもいましたし、もちろんそういうところを目指しながらミュージカルを学んでいたつもりだったんですけど、多分全然合ってなかったと思います。私の性格も考えると一人があっていたのかもしれないと今では思います(笑)。
――舞台から離れようと思った時期はありますか。
源川 心底ではないかもしれない。だけど歌のレッスンとかで幾度となく挫折はあるし、役に対して自分の理想通りにできないもどかしさみたいなのとか、そういった葛藤はずっとあります。けれどもちょっとでも理想に近づいていくことが楽しみでもあると思うし、それができている環境っていうことがすごくありがたいなって今は思ってます。
――1つの物語をほとんど一人で完結させていくっていうのはすごく大変ではないかと想像します。
源川 大変よ。でも考えないようにしています。考えるとプレッシャーがすごいじゃないですか。だからあんまり考えないで能天気でいられるというところも備わった長所なのかなって。
――もともとこういった文学作品に親しみがあったんですか。
源川 いえ、実は国語苦手だったんですよ。本を読むより外で体を動かしたいという典型的な体育会系でした。だから自分が今文芸作品をやっているというのがおかしくて(笑)。今でも色んな方に教えて頂いています。今ある「源川瑠々子」の中身は、沢山の方から頂いた言葉や経験でできていると強く感じます。
――源川さんは今年で舞台生活が20周年と大きな節目を迎えましたが今感じることは。
源川 20年間でいろんな方がついてきてくださって理解してくださって、作品もたくさん神尾先生が作ってくださって、本当に幸せな20周年を今迎えているなと思います。
次の20年も周りにいてくださる皆さんと一緒に元気にひとり文芸ミュージカルを続けていられることを願っています。そして次の人に継承していくという意味でもひとり文芸ミュージカルというジャンルを確立していかなきゃいけないなと強く感じています。ただ私教えるのが下手なので、そこは今後の大きな課題です。
――今回、ひとり文芸ミュージカルの演出を手がけられている神尾憲一さんも同席しています。神尾先生、いかがでしょうか。
神尾 実は来年ワークショップをやる予定なんです。
――どういう内容になりますか?
神尾 着物の着方とか、歌のレッスンもやります。普段着物とかになじみがないと……例えば扇子を渡されたら困りますか? はい。(渡される)
――え、広げて仰ぐくらいですかね。持ち方とかがあるのでしょうか。
源川 まずは扇子の表を自分の方にせず、相手側に。和の心ね。
それから仰ぎやすいから親指を外側にしてもつ人が多いのだけれど、実はこの持ち方は「男持ち」と言われています。もちろんそうやって仰ぐ時もあるけれど、親指を内側にして他の手をそろえて。本来こうやって女性は仰ぎます。さあやってみて。
――ちょっと仰ぎづらいです。
源川 下の方に左手を添えて…。そうそう。仰ぎづらければ手の位置を下げたり角度を変えてみたりして、やりやすい場所を見つけてみてください。どっちの方法であおいでもかまわないのだけれど、知っててやるのと知らないでやるのは違ってくるんですよね。
――教えていただいたことを意識して仰いでみると、少し優雅な気持ちになります。(閉じて返す)
源川 閉じるときは、相手がいればちょっと避けて閉じると美しいです。着物を着ている場合、帯にさすので流れがきれいに見えます。(扇子を開く~閉じて帯にさすまでの動作をする)
――本当だ。一連の流れが美しいです。というか、源川さん教えるのすごくお上手ではないですか! 今のお話非常にわかりやすかったです。
源川 本当ですか。こういうことでいいのなら教えられるんですけど、ちゃんとした舞台となるとねえ。でも私も楽しかったわ(笑)。
源川瑠々子(みながわ・るるこ)
2003年3月、夏目漱石の「こころ」を原作にしたミュージカル「もうひとつの、こころ」プレビュー公演でデビュー。作品は、瀬川昌久氏の提案で、ひとり文芸ミュージカル「静-shizu-」と改められ、同年10月に本公演を日本橋劇場で開催。また、平行して美しい日本語をモットーに、島崎藤村の詩集を歌うリサイタルの開催や和小物作家として作品を製作するなど活動の幅は多岐にわたる。
グッとグルメの新着記事
-
山崎真由美さん
洋食Bistro時遊 ポークジンジャーのランチ 7年前にできた店です。知り合いだった店長に頼まれて娘がアルバイトをしていました。私が初めて店を訪ねた際も働いていました。以来、月1回くらい足を運びます。 -
伊原六花さん
慶希処みおや 蜜芋のけいき ツマイモが好きで長年いろいろなスイーツを求め続けた伊原さんが心に刺さった「けいき」 -
平野ノラさん
焙煎職人 鈴木正美の店 職人アイスコーヒーリキッド アイスコーヒーの酸味や後味が苦手でカフェラテ派でした。でも5年ほど前に先輩芸人のナイツ・塙(宣之)さんからいただいた「職人アイスコーヒーリキッド」を飲んで、「こんなにおいしいんだ!」と驚きました。 -
円井わんさん
カフェ・ドゥ・アンサンブル 納豆チーズトースト 34種類のトーストとサンドイッチが常時あるので、いつも迷います。定番なら「納豆チーズトースト」。
新着コラム
-
食彩を描く 澤田瞳子の滋味探訪 何杯でも食べ歩く 沖縄のヒンヤリ「ぜんざい」 直木賞受賞作『星落ちて、なお』などで知られる澤田瞳子さん。実はご当地グルメを見ると目の色が変わってしまう、という秘められた生態の人です。そんな作家を唸らせる滋味の数々――なかでも「ここまでハマっている甘味はない」と断言する沖縄のぜんざいをご紹介します。
-
私の描くグッとムービー 徳持耕一郎さん(造形作家)
「サウンド・オブ・ミュージック」(1965年) 初めての海外は、欧州への貧乏旅行でした。当時、僕はアートへの情熱が抑えきれず、鳥取大学工学部を中退。東京の専門学校で版画をイチから学んでいましたが、若さゆえの焦りがありました。 -
-