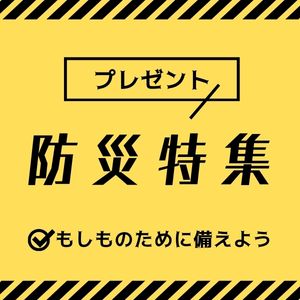群馬県立館林美術館
動物らしさ 簡潔に美しく

動物彫刻は従来、写実的表現が伝統的でした。滑らかで洗練されたフォルムの動物彫刻により歴史を一新した作家が、フランスのフランソワ・ポンポン(1855~1933)です。当館では彫刻60点、素描7点を所蔵しています。
パリの動物園やノルマンディー地方で動物を観察して、その場で粘土で形を捉えるのが、ポンポンの創作スタイルでした。動物を愛した作家として知られ、動物園では動物が懐いて寄ってくるほどでした。
ポンポンはある朝、逆光の中で見たガチョウのシルエットの美しさに感銘を受けて、表面が滑らかで美しいシルエットの動物彫刻を作り始めます。師匠のロダンが動きとボリュームを大切にしたように、あくまでその動物らしさをとどめながら簡潔に表現したのです。
ポンポンは1922年、石膏(せっ・こう)製で実物大の「シロクマ」をサロン・ドートンヌに発表し、表現の独創性が注目を集めます。簡潔なフォルムを好む当時の美意識も影響していたでしょう。当館の「シロクマ」は同じ形を縮小した大理石製です。大理石製は13点作られましたが、当館の作品の石は光を反射する粒子を含んでいるのが特徴です。
制作当初、右前脚は前に出ていましたが、後ろに下げて重心を中央にしたと考えられます。動物としてのリアリティーと、作品としての安定感の両方が絶妙なバランスで成立しています。脚やかかとのシャープな線も、ポンポンの美学といえるでしょう。
「バン」は水辺で暮らす鳥です。水かきがなく泳ぐのは苦手ですが、脚はしっかりとしていて凸凹した水辺を歩くのは得意。作品は、バンの前のめりに歩く姿勢が美しい輪郭線の中に表現されています。
(聞き手・深山亜耶)
《群馬県立館林美術館》群馬県館林市日向町2003(☎0276・72・8188)。午前9時半~午後5時(入館は30分前まで)。原則(月)、年末年始休み。別館「彫刻家のアトリエ」は、ポンポンのアトリエを再構成している。

学芸員 松下和美 さん まつした・かずみ 仏リール第3大学美術史専門研究課程修了。2004年から現職。専門は西洋近代美術。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
世田谷美術館 40年前の開館当時から 「日々を豊かにする美術」を発信し続けた逸品
-
鶴岡市立藤沢周平記念館 「ごますり」「ど忘れ」「祝(ほ)い人(と)」ーー連作短編集「たそがれ清兵衛」は8編それぞれ、特異な物腰や風貌(ふうぼう)、極端な性格ゆえにあだ名をつけられた武士が主人公です。
-
日本オリンピックミュージアム 日本オリンピックミュージアム
-
カスヤの森現代美術館 森の中で開眼。戦後アートシーンを代表する現代アートに触れる
新着コラム
-
-
グッとグルメ 古川昌希さん
イタリア料理ブカティーニ ビーフピラフ 小学生の頃から通っている大好きなお店です。ピラフと言えばパラパラご飯のイメージですが、これはしっとり系。今まで食べたことのないピラフでしたね。 -